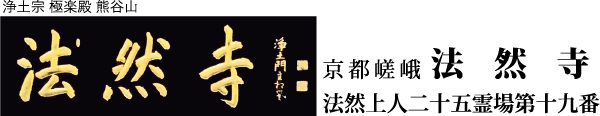熊谷次郎直実は、平家追討の合戦に名をあげたが、世の無常を感じ法然上人を師と仰いで51歳の時に出家し、法力房蓮生「ほうりきぼうれんせい」と改名した。
蓮生は、念仏の法門に深く帰依したので法然上人から、ご自作の尊像を賜り、それを奉持して故郷の埼玉県熊谷市に下向したが、その後に霊告を受けて再び京洛に奉安して熊谷山 法然寺と号した。
以来、たびたび兵火に遇うたが、幸いにも尊像は、ここ嵯峨野の地に、久しく安置されている。
法然寺の歴史

法然寺は京都市内の真ん中、四条烏丸錦小路現在の地名の「元法然寺町」にありました。その後の法然寺は、正応年間(1289~1292)には、ご病気であった第92代伏見天皇からの手厚い加護を受け、極楽殿の称号を賜り、続いて第105代後奈良、第106代正親町天皇の勅願寺となる。その間には足利義政や豊臣秀吉からの扶助も受ける。徳川幕府から三百石と御朱印を拝した。・・・・・・
法然寺の宝物

法然上人の肉牙の舎利
《非公開》
《非公開》
《公開中》
平敦盛の像
熊谷次郎直実は出家後に、この仏像を作り、時間の許す限り、常に丁重な追善回向をしておりました。
第92代伏見天皇より賜る。
【極楽殿】
その後には【第105代後奈良天皇の勅願所】【第106代正親町天皇の勅願所】・・・